私たち夫婦は、マイクロ法人を通じて4棟のアパートを運用しています。最初の2棟を法人設立時に購入し、その後、5年目に3棟目、7年目に4棟目を追加しました。現在、税引き前のキャッシュフローは500万円に達しています。本日は、この投資拡大の経験についてお話しします。
投資目的と方針
アパート購入で最も重要なのは、その目的を明確にすることです。当時、私のサラリーマン収入だけで6人家族を養っていたため、リスク分散として複数の収入源が必要でした。株式投資や日本国債での運用を試みましたが、期待した成果は得られませんでした。私たち夫婦は、子育て期間から老後まで続く、数十年にわたる安定的なキャッシュフローを求めていました。具体的には、もう一人の働き手に相当する年間500万円のキャッシュフローを目標としました。この目標から、方針は自ずと明確になりました―50年以上の超長期保有です。短期売買は一切行わない方針です。また、定期的な物件視察を考慮し、現在および将来の居住地である首都圏内での物件取得を決めました。
長期保有に向けたリスク回避のスクリーニング
土地編
- 人口減少リスクの高い地域は候補から除外しました。具体的には、首都圏の東京主要駅(品川駅、渋谷駅、新宿駅、東京駅、上野駅など)までの通勤圏内(60分以内)で、駅から徒歩15分(1.2km)以内の土地を探しました。
- 水害リスクのある地域も除外しました。ハザードマップで確認できる情報です。不動産会社には「重要事項説明書に含まれる水害リスクを事前に開示してほしい」と伝えれば、詳細な情報を得られます。
- 東京23区内も最初から除外しました。地価と家賃のバランスが取れないためです。建物の建設費用は場所による差が小さいものの、土地代は地域により大きく異なります。しかし、家賃は土地代の差ほどには上がりません。土地価格は建物価格と同程度までに抑えることが望ましいと判断しました。特に土地は減価償却できず、固定資産税も発生するためです。結果的に税引き後利回りに影響します。
建物編
- できれば30㎡、最低でも25㎡の部屋を作ることができ、風呂トイレは別であること。これがあれば、築古になっても十分需要があります。極小アパートも一定の人気があるとは思いますが、無理があります。
- 流行に左右されないシンプルなデザインであること。時々お城の様なメルヘンチックなものを勧める不動産会社がありますが、長期間万人受けするように思えません。
物件選びの方法
明確な投資目的と方針に沿って、追加の2棟を時間をかけて慎重に探しました。10社の不動産会社と連絡を取り、直接面談して提案を聞きました。ここでは、私たち夫婦の物件選びの考え方をご紹介します。
マーケットの規模と成長性を推測
日本は人口減少社会に向かっていますが、単身世帯は横ばいか増加傾向にあるため、単身者向けアパート賃貸市場に焦点を絞りました。具体的には、年収300万円~500万円で、自家用車を必要としない層をターゲットとしました。このような人たちは朝から夕方まで働き、休日は自宅で過ごすか近所に出かける傾向があります。自宅での滞在時間は短いものの、在宅時は快適に過ごし、仕事に向けて心身を整えたいというニーズがあります。また、月額5~7万円の家賃負担が可能な層です。
次に最寄り駅の規模を検討します。駅の1日あたり乗降者数はWikipediaで確認でき、10年前との伸び率から将来性を判断できます。10%以上の減少は要注意としました。理想的なのは1日の駅利用者が5万人を超える規模です。このような駅周辺には仕事の需要も見込めます。5万人規模の駅でなくても、そこまで15分以内で通勤できる駅も重視しました。ただし、乗降者数が2万人を下回る駅は避けました。
これらを考慮し、30㎡前後(最低でも25㎡)で風呂トイレ別の1K物件が望ましいと判断しました。キッチンと居室の区切りは必須とし、さらに自宅Wifiを月額無料で提供することにしました。
競合から適正家賃を推測
不動産会社の提案は競合と比較して検討しました。賃貸検索サイトで駅を選び、賃料・専有面積・間取り・駅徒歩・築年数・建物構造などの条件で検索すると、競合物件が表示されます。100件以上表示されても驚く必要はありません。同じ物件が複数の賃貸会社によって重複して登録されているためです。これらを分析すると、駅からの距離や築年数による家賃の変動など、一定の法則が見えてきます。これにより、提案された家賃の適正さを判断できました。新築アパートの建築ラッシュは、むしろ市場の成長性を示す良い指標と捉えました。
適正な利益の確保
期待する利回りは最低でも5.0%を目標としました。新築または築浅物件で、10年は大規模修繕が不要という前提です。計算方法は、利回り=(期待する家賃収入-運営経費) ÷ (総投資金額)です。不動産会社との話し合いでは、利回りの定義を確認し、各項目を詳細に確認しました。あいまいな回答をする会社とは以降の面談を取りやめました。
利回り=(期待する家賃収入-運営経費) ÷ (総購入費用)
- 期待する家賃収入=満室時の想定家賃収入×90%(10%の空室リスクと家賃下落リスクを考慮)
- 運営経費=支払利子+管理費+固定資産税+賃貸広告費(賃料の1か月分)+火災・地震保険料+共用部分の水道光熱費+Wifi
- 総購入費用=土地代+建物代+購入諸経費代(登記費用、不動産取得税、仲介手数料、銀行手数料)
また、借金返済後の手元に残る年間キャッシュフローは500万円を目標としました。計算方法は以下の通りです。
キャッシュフロー=(期待する家賃収入)-(運営経費+返済金額+税理士費用+バーチャルオフィス費)
返済金額は銀行との返済期間の設定が重要です。長期返済は短期的な手残りが増えますが、短期返済は総支払利子を抑えられます。
値段交渉の実際
様々な理由をつけて値下げ交渉を試みましたが、新築物件では全く効果がありませんでした。一方、中古物件の仲介では十分な交渉の余地がありました。
新築のケース
販売価格は固定で、営業担当者に価格決定権はありませんでした。これは私のサラリーマン時代の経験からも理解できます。営業担当者に価格決定権を与えると値崩れを起こすため、不動産のような高額商品では価格決定権を営業から切り離すのが賢明です。値下げ交渉を試みましたが、まったく通用しませんでした。
ただし、不動産会社側に早期売却の事情がある場合は、最初から値下げされた価格で提案されることがあります。実際、私が購入した物件はそのようなケースでした。当初は購入予定者が決まっていましたが、銀行融資の審査で不正が発覚し、契約が不成立になった直後の物件でした。完成まで2か月という時期で、値下げ後の価格だったため、相場より割安と判断し、その場で銀行に融資の相談をしました。不動産会社の営業担当者からは「強運の持ち主ですね」と評価されました。良い物件は即断即決が重要で、素早い行動が営業担当者の強力なサポートにつながります。
中古の仲介のケース
売主は多くの場合、価格を高めに設定していました。期待利回りや修繕費用を根拠に値下げ交渉をしました。具体的には300万円の値下げと階段のペンキ塗装を要望しました。希望利回りから逆算した価格提案には説得力がありました。また、雨にさらされる鉄製階段には必ずサビが出ます。構造上の問題はありませんが、見た目が損なわれるため、引き渡し前の塗装を依頼しました。両方の要望が承諾され、買付けに至りました。
銀行融資の実際
私たち夫婦は3棟目をメインバンクから、4棟目を新規取引の信用金庫から借り入れました。いずれもプロパーローンでの融資です。
メインバンクから(3棟目の新築)
メインバンクには毎年、マイクロ法人の決算報告と個人の確定申告を提出しています。追加融資の可能性も定期的に確認していたところ、「案件次第で十分可能」との回答を得ていました。具体的な案件が出たため、支店に連絡し、必要書類一式を即座に提出しました。総額9600万円の融資は、買付けから金銭消費貸借契約まで6週間という短期間で実現しました。劣後対策等級3(親子3世代の75-90年間、大規模修繕不要)の認定により、金利0.80%、返済期間30年という好条件を引き出せました。
信用金庫から(4棟目の中古)
メインバンクからは前向きな回答が得られなかったため、不動産会社の紹介で地方銀行と信用金庫に相談しました。銀行開拓は自力でする方もいますが、不動産会社からの紹介が最も確実です。一度関係が構築できれば、その後は直接案件を持ち込めます。
地方銀行での仮審査は、融資額の制限や金利面で条件が折り合わず、見送りました。この時点で優先順位の見直しが必要でした。この中古アパートは老後の安定的なキャッシュフローを目的としているため、融資期間を短くし、多少の高金利を受け入れても、実質的なキャッシュフローがプラスなら購入する方針に切り替えました。最終的に、16年返済、金利2.475%で3200万円の融資を受け、自己資金1500万円を投入して購入を決定しました。
今後の方針
これらアパート4棟の運用により、マイクロ法人の税引き前キャッシュフローは年間500万円を達成しました。不動産投資は一般的な投資と異なり、事業性が強く、相当な労力を要します。当初の目標を達成できたため、今後は新規物件の購入を控え、既存物件の運用に注力する方針です。
次回は、銀行からの金利上昇への対応策についてお話しします。
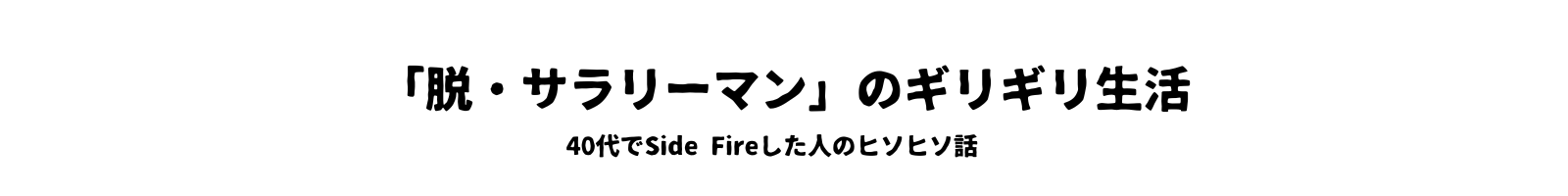



コメント