長年にわたりゼロ金利時代の恩恵を受け、低金利での資金調達を行ってきました。しかし近年、日本国債10年物に連動して金利が上昇傾向にあります。私たち夫婦のマイクロ法人が抱える2億円の残債にも、金利上昇の波が容赦なく押し寄せています。今日は、銀行からの利上げへの対処方法についてお話しします。
利上げへの牽制
私たち夫婦は2つの銀行と取引があります。メインバンクは5年固定後の金利見直し、サブバンクは変動金利です。メインバンクでは0.75%の融資を受けていましたが、2022年の5年固定金利更新時に0.80%への引き上げを打診されました。2億円近い残債では、わずか0.05%の上昇でも年間10万円の負担増となります。金額は大きくありませんが、これが今後の融資全般の基準となります。この状況では金利上昇を断ることはできませんでしたが、代わりに良い条件を引き出そうと新規融資を提案しました。ただし、当時はコロナ禍の影響が残る時期で、支店は新規融資に慎重でした。金利条件が悪化する際は、代替条件を引き出すのは事業として当然の対応です。安易に「いいですよ。しょうがないですよね」と受け入れると、以降も遠慮なく利上げが押し寄せてきます。ごねるのではなく、正当な牽制をするのが適切なのです。最終的に、地元の信用金庫で4棟目のアパートを購入することになり、金利は2.475%と高めでしたが受け入れました。他の銀行との取引実績を作ることは、将来的な交渉力にもつながると考えています。
借換の相談
2024年に入り、日本国債10年物の利回りは上昇を続け、遂に1.0%に届きました。地元の信用金庫からの融資は1年経過後、一通のハガキで2.850%への金利引き上げが通知されました。これにより、銀行による一方的な値上げの実態を知ることとなりました。変動金利の性質上、営業窓口への抗議も効果はありません。メインバンクに相談したところ、担当者は誠実に対応し、支店稟議に向けて共に書類作成に取り組んでくれました。しかし、借換の稟議は通らず、最近の市況悪化で借換も困難な状況です。
家賃に転嫁
最後の対策として家賃への転嫁を選択しました。仕入れコストが上昇すれば、それを価格に反映するのは当然です。価格転嫁には主に2種類あります。現入居者の契約更新時の値上げ提案と、退去後の新規入居者募集時の値上げです。不動産管理会社には「金利上昇分の価格転嫁は必須であり、家賃値上げか管理費削減のいずれかを検討するのは経営者として当然。御社が真のパートナーとして共に歩めるかを確認したい」と伝えました。
現入居者の家賃値上げ
通常、値上げはシェア低下を招きます。そのため、新価格への移行期間中はクーポン配布などの対策が必要です。例えば、家賃を6万5千円から6万8千円に上げる場合、3千円(4.6%)の値上げとなります。しかし、10室中1室が退去し、1か月の空室期間と広告費用が発生すれば、むしろマイナスとなります。これが値上げの難しさであり、私もサラリーマン時代に同様の経験をしました。不動産管理会社に相談しましたが、真のパートナーとしての積極的な姿勢は見られませんでした。
新入居者募集時の値上げ
2部屋の退去が発生し、不動産管理会社から「3千円の値上げで募集してみましょう。ただし、7万円を超えると物件検索から外れるリスクがあるため、6万9千円までが妥当です」との提案がありました。営業姿勢には疑問が残りましたが、競合物件の家賃状況を考慮すると、受け入れられる提案でした。そこで、新しい家賃での募集を開始することにしました。現在(2025年1月1日)は入居者の退去前ですが、結果が出次第、当ブログで報告いたします。
アパート経営は投資ではなく、れっきとした事業です。サラリーマン時代に培ったマネジメント力、会計知識、コミュニケーション能力を活かし、適正な利益確保に努めています。
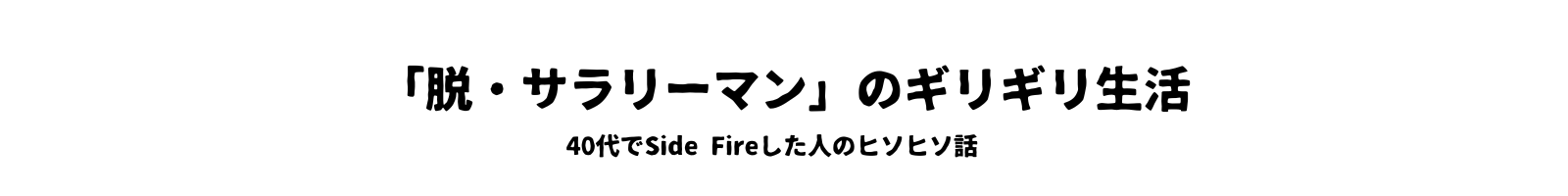



コメント