不労所得という言葉の方がしっくりくるかもしれませんが、実際には何も作業をせずにお金を得られるわけではないため、ここでは資本所得と呼びます。2013年から2024年の間で私たち夫婦が経験した投資の利益についてランキング形式でお話しします。なお、マイクロ法人としての不動産賃貸業は除外し、個人として取り組んだものに限定します。
1位 株式譲渡益と配当
パフォーマンス
税引き後利益は516万円(2013-24年)で、そのうち200万円は2013年のアベノミクス期待による株価急騰時に得たものです。
取った行動
戦略はなく気分で売買でした。株価が小幅上昇時に利益確定し、下落時は長期保有という結果でした。株主優待狙いやスイングトレードも試みましたが、相性が合わず早期に断念。成功例はアベノミクスに乗ったことやコロナショック時の押し目買い程度で、2023年以降の株価急騰の機会も活かせませんでした。
学び
2008年のリーマンショックと東日本大震災の頃の株価下落による損失経験から、株式投資への積極性を失いました。自身の性格が株式投資に適していないことを認識し、短期売買のギャンブル的な性質も考慮して、余剰資金の投資先をマイクロ法人への不動産賃貸業向け貸付へと転換しました。
2位 ソーシャルレンディング分配金
パフォーマンス
税引き後利益は140万円(2018~23年)で、年平均23万円の収益となりました。
取った行動
子供たち4人の口座にある余剰資金(親戚からのお年玉貯金と私からの贈与金)を活用しました。一人100万円の元手で総額400万円となり、親権者として管理・運用を行いました。年利6-8%で運用し、子供たちの所得なので正しく還付申告を行いました。税金がかからないメリットを実感しました。各々の年間所得は数万円程度でしたが、人数と期間を重ねることで大きな金額となりました。利益は再投資か、子供たちの必要な物品購入に充てました。
主婦である妻も参加し、人気銘柄の「クリック合戦」にも対応。募集開始から1分で完了する案件も多くありましたが、うまく対応できた様でした。
リスクを考慮して独自の銘柄選択基準を設け、償還遅延は数件経験したものの、長期未償還は9,600円の1件のみでした。
学び
私たち家族の投資スタイルに適していました。確定申告と還付申告は必須でしたが、投資効率は良好でした。現在は子供たちの学費需要があるため、ソーシャルレンディングは停止しています。
Maneoファミリー 老舗のManeoとLCレンディングに投資し、償還遅延は数件ありましたが、全額回収できました。
クラウドバンク 親子での口座開設が可能な数少ないソーシャルレンディングでした。6年間、子供たちの資金を親権者として運用し、償還遅延もなく安定した収益を得られました。
CREAL 不動産系のプラットフォームで、妻が長期間利用。期限前償還は多かったものの、最も安定した運用実績でした。
Ownersbook 高評価の割に苦戦しました。低利回り(4-5%)にもかかわらず、関西地方の案件で長期遅延が発生し、不安な期間を過ごしました。現在も全額償還には至っていません。
SBIレンディング ソーラー案件で収益を上げていましたが、コンプライアンス上の問題でサービスが突然終了。実害はなく、悪印象は残っていません。
みんなで大家さん 安定した運用益が得られましたが、不動産購入資金の必要性から途中解約。解約手続きと返金は円滑に完了しました。厳密にはソーシャルレンディングとは違うと思いますが、ここに分類します。
3位 小規模私募債の配当
パフォーマンス
税引き後利益は70万円(2023~24年)で、年平均35万円の収益となりました。
取った行動
知人が経営する企業の私募債です。投資の検討を持ちかけられ、企業の財務諸表を精査した結果、倒産リスクが低いと判断し、600万円を投資しました。
学び
年率8%の利息に加え、20.315%の源泉分離課税という税制面でのメリットが気に入っています。3年償還は少し長いですが、購入を2回に分散しているので償還時期も分散しています。
税務処理について税理士に確認したところ、「預金利息同様、利子所得として20.315%の源泉分離課税が適用され、確定申告は不要(不可)」との明確な回答を得ました。
信頼できる発行体による小規模私募債は、有効な投資選択肢だと考えています。手間がほぼないので、今後も余剰資金を継続投資します。
番外編
日本国債 証券口座で個人国債(変動10年)を2014年から2016年まで500万円保有していました。当時は空前のゼロ金利時代で、受け取った利金は合計2万円程度でした。現在の金利環境はより良好だと考えています。
生命保険の終身保険 20代の頃、最低2%の運用利回りを提示されて加入し、毎年保険料を支払っています。65歳までの支払総額は2000万円、受取予定額は3000万円です。しかし、支払額と返戻金予定額が同額になるのが59歳という点や、受取時の利益分が課税対象となることから、継続の是非を検討中です。子供たちの就職後は生命保険の必要性が低下するため、その時点での解約も視野に入れています。
アクティビストファンド 企業変革を促す社会的意義に共感し、1000万円を投資しました。株主として企業に積極的に関与する投資手法に魅力を感じ、3年間継続しましたが、結果的には損益ゼロで終了しました。
今後の方針
脱・サラリーマンの私は資金繰りが厳しくなってきており、余剰資金は限られています。リスク、リターン、作業量を総合的に評価した結果、現在保有している小規模私募債は満期まで継続保有します。満期時に新規募集があれば償還金を再投資し、それ以外の投資機会については見送る予定です。
前回は家族の労働所得について、今回は家族の資本所得についてお話ししました。次回は、家族の支出をどのように抑制してきたかについてお話しする予定です。
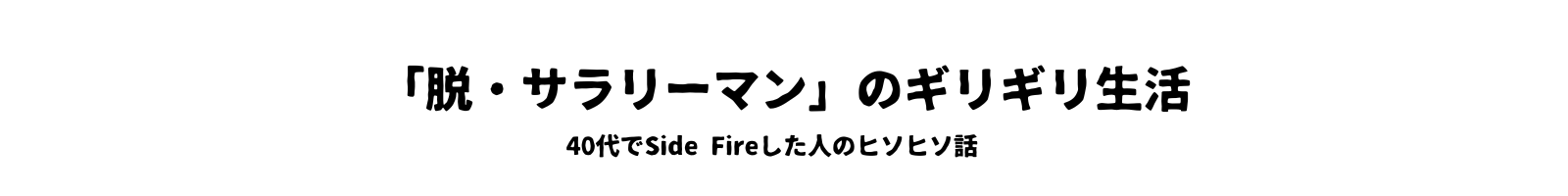



コメント