妻の就活
妻は国立大学卒の理系女子です。就職氷河期でブラック企業に就職しましたが2年で寿退社し、その後4人の子供に恵まれ、全員中学校卒業まで育てました。
末っ子が中学校を卒業する前、私は妻にこう宣言しました。「私はサラリーマンを辞める。収入が激減するから、妻働け!」
妻は「なぜ私が働かなければいけないの?それなら離婚して財産分与よ!」などとは決して言わない性格です。
むしろ即座に「はい、分かりました。あまり稼げないと思いますけど、探してみますね」と答えてくれました。本当に良い人と結婚したと思いました。
それは、私がラットレースを20年以上続け、苦労に比例して増える税金、期待ほど増えない手取りに疲れ果てていた姿を、妻が隣でずっと見ていたからです。
妻は新卒から2年間の職歴の後、20年のブランクがありました。軽いアルバイトでもするのかと思っていましたが、現代社会はどこも人手不足でした。
首都圏に住んでいることもあり、求人を見ると募集が多く、未経験者歓迎、40代OK、時短勤務もOKという条件が目立ちました。
妻は「ゆるく」働きたいと考え、時短勤務で月給20万円未満で十分と考えていました。ちょうど大学で専攻していた分野の仕事を見つけ、すぐに履歴書を添えて応募しました。
簡単な面接を経て、すぐに正社員として採用が決まりました。就職氷河期の就活は何だったのだろうと思わされる出来事でした。
サラリーマン交代
私が脱サラリーマンをして間もなく、妻がサラリーマンになりました。まさにサラリーマン交代です。
脱サラリーマンとなった私は自分のペースで仕事ができるようになりました。家から出ない日もあり、朝は妻に「行ってらっしゃい」と言うことが増えました。これは私たち夫婦にとって新鮮な経験です。特に役割分担は決めていませんが、私が朝の洗濯、掃除機がけ、食器洗いをすることが多くなりました。週に2〜3日は夕食も作ります。妻とは違う味付けなので、子供たちも新鮮な味わいと好評です。今更ながら「令和の男」になり、家事による手荒れも気になるようになりました。
妻は朝から気持ちよく出勤していきます。社会での新しい人との出会いが良い刺激になっているようで、自信に満ち溢れ、颯爽と歩いていきます。毎日の通勤で体重も減り、より健康的になりました。時々の有給休暇も嬉しそうに取得し、会社での出来事も楽しく話してくれます。
お互いの生活のペースが程よく調和するようになりました。互いに暇すぎず、忙しすぎず、助け合い、支え合いながら夫婦円満に過ごしています。
児童手当と所得分散のメリットを実感
2024年10月から児童手当が私たちにも復活しました。高校生二人分で年間72万円です。これには納税者の皆さんには感謝しています。私は児童手当は住民税の減税の様なものと考えています。具体的には翌年度の住民税から児童手当を引いた額として家計管理をしています。
2023年途中から私は経験を活かして中小企業の取締役に就きました。マイペースで仕事ができるものの、2024年の労働収入は810万円まで減少しました。妻の就職により世帯収入は1005万円となり、可処分所得は893万円、可処分所得率は88.8%です。高校生から大学生までの4人分の扶養控除と定額減税が今年の可処分所得に寄与しています。前述の児童手当と合わせて、88.8%という高い可処分所得率を達成できました。状況が異なるため単純比較はできませんが、家庭での可処分所得の減少は602万円に抑えられ、十分に満足できる1年となりました。2022年の激務に対する可処分所得と比べても本当に満足です。
| 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2024年-2023年 | |
| 世帯収入 | 3199万円 | 2121万円 | 1005万円 | -1116万円 |
| 可処分所得 | 2014万円 | 1495万円 | 893万円 | – 602万円 |
| 可処分所得% | 63.0% | 70.5% | 88.8% | +18.3%pt |
可処分所得=(労働収入+資本収入)-(所得税及び復興特別所得税+社会保険料+ふるさと納税+翌年度の住民税-翌年度の児童手当)として算出。
世帯の可処分所得が90%近くになると、精神衛生が著しく改善されます。支払う税金に対する費用対効果が非常に良いのです。社会保険料は153万円の支払いでしたが、家族の通院や将来の年金増額を考えると、この程度の支出は妥当です。取締役は雇用保険に加入しないため、これは免除されます。実際、私は雇用保険を一度も利用したことがありません。翌年度の住民税は25万円程度の見込みですが、それ以上の児童手当が見込めます。国税負担も数万円程度で済むため、使途についても特に不満は感じません。
子供たちの義務教育終了とともに、妻がサラリーマンになれて本当に良かったと思います。妻には過度な競争に巻き込まれることなく、給料にもこだわらず、程よいペースで働き続けてほしいと願っています。
これで「脱・サラリーマン」への道は終了です。次回は「脱・サラリーマン」を実現できた夫婦のお金の管理についてお話します。
#脱サラ
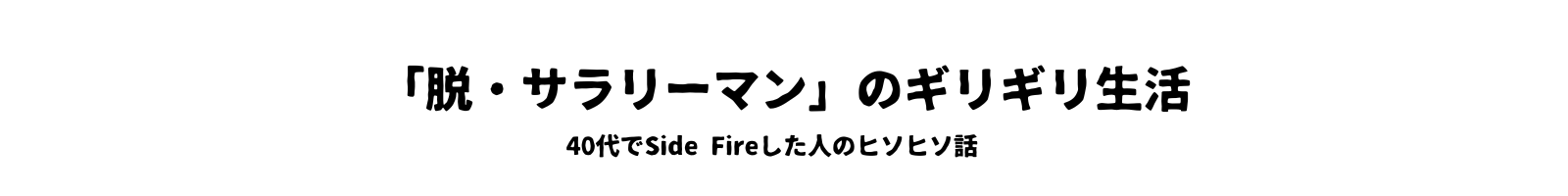



コメント