サラリーマン時代
22年間のサラリーマン生活に終止符を打ち、「脱・サラリーマン」を決意しました。サラリーマン時代は大企業の上級管理職で、給料とストックオプションで年収2000万円を毎年超える生活。給与所得者の上位0.5%の年収だったそうです。「なぜ辞めるの?もったいない」とよく言われました。
しかし、現実はどうだったでしょうか。早朝から電車で片道1時間以上かけて通勤し、8時から19時まで猛烈に働き、また長時間電車に揺られて帰宅。家に着いても仕事は続き、土日も溜まった業務をこなす日々。ストレスによる暴飲暴食でメタボ体型となり、家では不機嫌な父親に。
「家族のために我慢すれば、いつか子育ても終わる」「あと10年だ」という呪文を唱え、これも仕方ないことだと自分に言い聞かせ、毎朝むりやり起き出し、二日酔いのまま家を出る生活。皆さんも似たような状況ではないでしょうか。
2022年の給与は3073万円でした。この年はストックオプションが大きく化けた特別な年。しかし手取りは1888万円で、納税率は39%でした。
税金と社会保険料:合計支払額:1185万円
- 所得税及び復興特別所得税の額:715万円
- 社会保険料:170万円(子供の国民年金保険料含む)
- ふるさと納税:100万円
- 翌年の住民税:200万円
確定申告と住民税通知による
大学生と高校生の扶養控除と医療費控除で、なんとかこの金額で済みました。ただし、中学生は児童手当がないのに扶養控除対象にもならないという矛盾した状況でした。
「もう疲れた。いつか辞めてやる」—これが多くのサラリーマンの本音ではないでしょうか。
FIREへの準備
私はFIREを目指して準備を進めてきました。子育て終了と同時に52歳での早期リタイアを目標に、夫婦でゆっくり仲良く生きていく未来を思い描いて。
そのために最も重要なのは家計の把握です。私はPL、BS、CFの財務三表の手法を家計管理にも活用しています。経理のように全ての支出を1円単位でエクセルに記録し、項目別の予算と実績を管理。10年続けることで将来の予測も可能になりました。子育て終了までの必要額、年金受給までの必要額、老後資金の試算—家計の現状と将来の把握は不可欠です。
家計の損益計算書であるPLを見ながら、次の3点をよく考えました。
- 労働所得を増やす(例: 給与)
- 資本所得を増やす(例:株式配当)
- 支出を減らす (例:家賃、車両費)
昇給・昇格・高ボーナスを目指して働き、適切な節税を実施。税務署への相談、ふるさと納税の最大活用、倹約生活の実践、車の非保有、株式投資による値上がり益の獲得と配当収入など、様々な方法を試みました。
最も効果的だったのは資産管理会社を設立してのアパート経営でした。総額2億5千万円の融資でアパート4棟を購入。年間家賃収入2000万円のうち、融資返済・管理経費・税金を差し引いた手取りは約600万円です。法人化により社宅制度を活用し、法人として借りた住居に社宅として居住。これにより家計支出の2割を占める住宅費の約80%を削減できました。また、アパート経営に携わる妻には年間99万円の役員報酬を支払ってきました。
「脱・サラリーマン」への一歩を踏み出す
45歳のとき、ある創業期の中小企業から取締役募集の話が舞い込みました。現物株は付与されるものの給料は3分の1に減少、経営の安定性も心配な会社でした。しかし、家計の純資産が6500万円(資産管理会社の資産を除く)まで積み上がっていたため、本格的なFIRE前のSIDE FIRE的な経験も悪くないと考えるようになりました。4人の子供全員が大学院修士課程を修了するまでの資産推移を何度もシミュレーション。資金的には何とかなりそうだという結論に至りました。最終的に決断を後押ししたのは3つの理由でした。
- Die with Zeroという本からの学びを生かそうと思った
- サラリーマン生活の「タイパ」に疑問を抱くようになった
- 子供の義務教育期間が終わり、妻をサラリーマンにできた
こうして大学卒業から22年間のサラリーマン人生に終止符を打ち、「脱・サラリーマン」への一歩を踏み出したのです。
次回はDie with Zeroという本からの学びをどの様に生かしたのかというお話をします。
#脱サラ
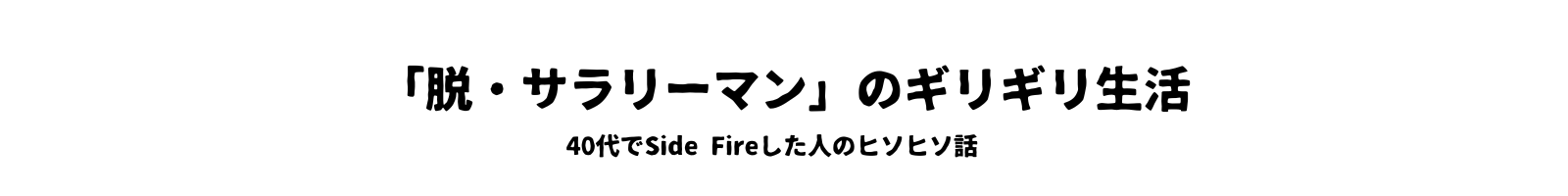


コメント